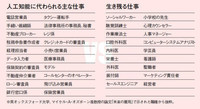2015年10月23日
『中小企業支援は、何が求められているのか?』その2
私の想いを書いておりまして、共感は嬉しいですが、反感もたくさん買うことかと思います。
しかし昨日に引き続き、想いを伝えさせていただきたいと思います。
その2も下記から引用いたします。
「千葉県産業情報ヘッドライン」
生き残りをかけた下請中小企業の自立化とは何か
https://www.ccjc-net.or.jp/headline/bn/h25/takayashiki.html
______________________________________
第2回 下請中小企業の自社製品開発について
下請企業であるメリットの一つに、新たな販売先を開拓する営業活動をしなくて
よいことがあります。
しかし、実はこのメリットこそが「自立化」の大きな障害になるのです。
一般的に、企業における受注業務の流れは次のようになります。
営業計画(企画)⇒営業活動⇒引き合い⇒設計⇒見積り⇒受注⇒製作⇒納品
これらの一連の流れを十分に対応できて初めて自立化が可能になるわけですが、
親会社から図面をもらってつくるだけの下請企業には、「見積り⇒受注⇒製作⇒納品」
しかありません。営業といっても社長の「御用聞き」だけです。
こういう会社が自立しようとしても、いったいどこに何を売り込んだらいい
のかわからず、途方に暮れることになります。
コスト的にも、営業不在の低販管費のコスト構造に慣れているため、現行の
販売価格ではとても販売費が回収できません。
長年こうしてやってきた企業が自社単独で新製品を開発しようとしても、市場の情報収集がうまくできず、「売れるはず」という仮説(思いこみ)の検証が不十分なまま商品化まで突き進んでしまいます。
その結果、発売後に想定した見込客を訪問しても、あるはずのニーズがなかったり、
ニーズがあっても、コストが全く市場に受け入れられないレベルになってしまっていて
失敗することがあります。
しかも、気が付いたときには多額の投資をしたあとで、回収の見通しが立たない
ということも少なくありません。
新製品開発の方向性を決めるのは、経営者の最も重要な仕事の一つです。
そして一度方向性を決めたあとも、絶えず顧客目線による軌道修正が必要です。
特に設備投資が必要な製品の場合は、徹底的な事前の検証が重要です。
上記の「取引の流れ」の中で、今の自社に欠けているものは何か、普段から考えて、
しっかりと体制づくりをしておきましょう。
最後に企業間連携による新製品開発についてお話します。
企業間連携とは、独自技術を持つ企業が、それぞれの「強み」を持ち寄り、弱みを
補い合って一つの新製品を開発することです。
最近、話題になった「下町ボブスレー」や深海探査機「江戸っ子一号」などは、
この代表的な事例です。
もともと中小企業では、仲間取引などで複数の企業が協力し合うことは珍しい
ことではありません。
しかし、この協力関係を必要に迫られてやるだけでなく、
独自性と志を持つ企業が意図的に集まって「新しい試み」を行うことで、脱下請への道を開くのです。
政府も補助金等で、この「連携」をいろいろな形で積極的に支援しています。
みなさんも身近なところから新しいシーズを見つけて挑戦してみませんか?
次回、第3回は、新製品開発と販路開拓についてお話しいたします。
B.Gコンサルティング 代表 高屋敷 秀輝(中小企業診断士)
___________________________________
昨年から、神戸でも「神戸航空機クラスター」が企業間連携を行っています。
紹介の動画を下記からご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=lj7X3K9gIOo
当初の想定通りにいかないことが多いですが、
「絶えず顧客目線による軌道修正が必要」だと思います。
なお、11月6日に行われる「神戸発・優れた技術」平成27年度認定証授与式・記念講演会では、
「魅力」発見の取り組みを人育てに活かす
3社の具体的取り組みを紹介し、その効果を発表いたします。
認定企業の皆様、ご参加をお待ちしています。
しかし昨日に引き続き、想いを伝えさせていただきたいと思います。
その2も下記から引用いたします。
「千葉県産業情報ヘッドライン」
生き残りをかけた下請中小企業の自立化とは何か
https://www.ccjc-net.or.jp/headline/bn/h25/takayashiki.html
______________________________________
第2回 下請中小企業の自社製品開発について
下請企業であるメリットの一つに、新たな販売先を開拓する営業活動をしなくて
よいことがあります。
しかし、実はこのメリットこそが「自立化」の大きな障害になるのです。
一般的に、企業における受注業務の流れは次のようになります。
営業計画(企画)⇒営業活動⇒引き合い⇒設計⇒見積り⇒受注⇒製作⇒納品
これらの一連の流れを十分に対応できて初めて自立化が可能になるわけですが、
親会社から図面をもらってつくるだけの下請企業には、「見積り⇒受注⇒製作⇒納品」
しかありません。営業といっても社長の「御用聞き」だけです。
こういう会社が自立しようとしても、いったいどこに何を売り込んだらいい
のかわからず、途方に暮れることになります。
コスト的にも、営業不在の低販管費のコスト構造に慣れているため、現行の
販売価格ではとても販売費が回収できません。
長年こうしてやってきた企業が自社単独で新製品を開発しようとしても、市場の情報収集がうまくできず、「売れるはず」という仮説(思いこみ)の検証が不十分なまま商品化まで突き進んでしまいます。
その結果、発売後に想定した見込客を訪問しても、あるはずのニーズがなかったり、
ニーズがあっても、コストが全く市場に受け入れられないレベルになってしまっていて
失敗することがあります。
しかも、気が付いたときには多額の投資をしたあとで、回収の見通しが立たない
ということも少なくありません。
新製品開発の方向性を決めるのは、経営者の最も重要な仕事の一つです。
そして一度方向性を決めたあとも、絶えず顧客目線による軌道修正が必要です。
特に設備投資が必要な製品の場合は、徹底的な事前の検証が重要です。
上記の「取引の流れ」の中で、今の自社に欠けているものは何か、普段から考えて、
しっかりと体制づくりをしておきましょう。
最後に企業間連携による新製品開発についてお話します。
企業間連携とは、独自技術を持つ企業が、それぞれの「強み」を持ち寄り、弱みを
補い合って一つの新製品を開発することです。
最近、話題になった「下町ボブスレー」や深海探査機「江戸っ子一号」などは、
この代表的な事例です。
もともと中小企業では、仲間取引などで複数の企業が協力し合うことは珍しい
ことではありません。
しかし、この協力関係を必要に迫られてやるだけでなく、
独自性と志を持つ企業が意図的に集まって「新しい試み」を行うことで、脱下請への道を開くのです。
政府も補助金等で、この「連携」をいろいろな形で積極的に支援しています。
みなさんも身近なところから新しいシーズを見つけて挑戦してみませんか?
次回、第3回は、新製品開発と販路開拓についてお話しいたします。
B.Gコンサルティング 代表 高屋敷 秀輝(中小企業診断士)
___________________________________
昨年から、神戸でも「神戸航空機クラスター」が企業間連携を行っています。
紹介の動画を下記からご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=lj7X3K9gIOo
当初の想定通りにいかないことが多いですが、
「絶えず顧客目線による軌道修正が必要」だと思います。
なお、11月6日に行われる「神戸発・優れた技術」平成27年度認定証授与式・記念講演会では、
「魅力」発見の取り組みを人育てに活かす
3社の具体的取り組みを紹介し、その効果を発表いたします。
認定企業の皆様、ご参加をお待ちしています。
ビジネスマッチングフェア2017が行われました。
働く女性のためのセミナー参加者の感想
神戸市が、若手社員に奨学金返済支援を行う中小企業を助成します
フィリピンは事業拡大が見込める市場?!
神戸創生戦略の実行に向けた海洋産業セミナーの開催
この企業の採用ページが分かりやすいです
働く女性のためのセミナー参加者の感想
神戸市が、若手社員に奨学金返済支援を行う中小企業を助成します
フィリピンは事業拡大が見込める市場?!
神戸創生戦略の実行に向けた海洋産業セミナーの開催
この企業の採用ページが分かりやすいです